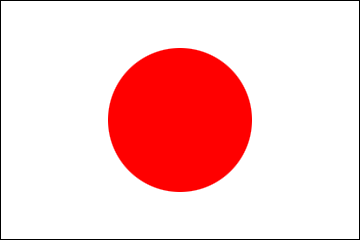ラトビアのユーロ硬貨
平成26年1月16日
2014年1月1日、ラトビアの通貨がラット(Lats)からユーロに変わりました。バルト3国では、エストニア(2011年1月導入)に次いでユーロ圏入りを果たし、18番目のユーロ導入国となりました。国家のアイデンティティとも関連しているラトビアのユーロ硬貨のデザインについて紹介します。
ユーロ硬貨は全部で8種類(1セント、2セント、5セント、10セント、20セント、50セント、1ユーロ、2ユーロ)あり、表面のデザインは共通のものが使用されていますが、裏面は各国で異なるデザインが施されています。8種類全て異なるデザインを採用している国(イタリア、オーストリア、ギリシャ、スロベニア)もあれば、全て同じデザインを採用している国(ベルギー、アイルランド、エストニア)もあり、デザインの種類は各国様々です。ラトビアの硬貨には、3種類のデザインがあり、1セント、2セント、5セントには「ラトビアの小国章」が、10セント、20セント、50セントには「ラトビアの大国章」が、1ユーロ、2ユーロには民族衣装を身にまとった「乙女の肖像」が施されています。これらのデザインは、ラトビア国民の「母国に対する愛」、「自由の探求」、「自国への誇り」を象徴するものとして選ばれており、その選考過程においては、「自由記念碑」も候補として検討されたようですが、限られたスペースで容易に認識できるように表現することが難しいとの判断により断念されたようです。
1ユーロ、2ユーロのデザインとなっている「乙女の肖像」は“ミルダ(Milda)“の愛称を持ち、ラトビア国民にとって自由の象徴の一つで、実は、戦前の1929年に発行された5ラット硬貨のデザインとしても使われていました。当時は、既に5ラット紙幣が流通していたため、“ミルダ”の5ラット硬貨は、機能面というよりもラトビアの「国家」と「自由」を象徴するものとして発行されたものでした。
その後、ラトビアは、ソ連、ドイツの占領下となり、その間、ラットは法定通貨から外され、“ミルダ”の5ラットを含む多くの硬貨が国外に流出しました。この状況下で、奪取から逃れラトビア国内に残った“ミルダ”の5ラット硬貨は、通貨としての機能は失いつつも、その美しさから、ブローチやペンダントとして愛用され、結婚式や洗礼式においては、誰もが欲しがる憧れのアイテムとなり、家宝として大切に保管されてきたそうです。“ミルダ”は、ブローチやペンダントの形で、ラトビアへの帰属意識や独立への希望を示す心の支えとして生き続け、そして、ユーロ硬貨として生まれ変わりました。
独自の通貨ラットは失われましたが、ラトビアのユーロ硬貨には、ラトビア国民の変わることのない「母国に対する愛」、「自由の探求」、「自国への誇り」が刻まれています。

自由記念碑
ユーロ硬貨は全部で8種類(1セント、2セント、5セント、10セント、20セント、50セント、1ユーロ、2ユーロ)あり、表面のデザインは共通のものが使用されていますが、裏面は各国で異なるデザインが施されています。8種類全て異なるデザインを採用している国(イタリア、オーストリア、ギリシャ、スロベニア)もあれば、全て同じデザインを採用している国(ベルギー、アイルランド、エストニア)もあり、デザインの種類は各国様々です。ラトビアの硬貨には、3種類のデザインがあり、1セント、2セント、5セントには「ラトビアの小国章」が、10セント、20セント、50セントには「ラトビアの大国章」が、1ユーロ、2ユーロには民族衣装を身にまとった「乙女の肖像」が施されています。これらのデザインは、ラトビア国民の「母国に対する愛」、「自由の探求」、「自国への誇り」を象徴するものとして選ばれており、その選考過程においては、「自由記念碑」も候補として検討されたようですが、限られたスペースで容易に認識できるように表現することが難しいとの判断により断念されたようです。
 「小国章(5セント)」 |
 「大国章(50セント)」 |
 「乙女の肖像(1ユーロ)」 |
1ユーロ、2ユーロのデザインとなっている「乙女の肖像」は“ミルダ(Milda)“の愛称を持ち、ラトビア国民にとって自由の象徴の一つで、実は、戦前の1929年に発行された5ラット硬貨のデザインとしても使われていました。当時は、既に5ラット紙幣が流通していたため、“ミルダ”の5ラット硬貨は、機能面というよりもラトビアの「国家」と「自由」を象徴するものとして発行されたものでした。
その後、ラトビアは、ソ連、ドイツの占領下となり、その間、ラットは法定通貨から外され、“ミルダ”の5ラットを含む多くの硬貨が国外に流出しました。この状況下で、奪取から逃れラトビア国内に残った“ミルダ”の5ラット硬貨は、通貨としての機能は失いつつも、その美しさから、ブローチやペンダントとして愛用され、結婚式や洗礼式においては、誰もが欲しがる憧れのアイテムとなり、家宝として大切に保管されてきたそうです。“ミルダ”は、ブローチやペンダントの形で、ラトビアへの帰属意識や独立への希望を示す心の支えとして生き続け、そして、ユーロ硬貨として生まれ変わりました。
独自の通貨ラットは失われましたが、ラトビアのユーロ硬貨には、ラトビア国民の変わることのない「母国に対する愛」、「自由の探求」、「自国への誇り」が刻まれています。

自由記念碑