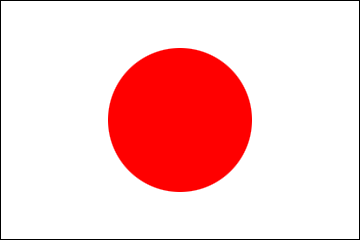ラトビアのマナー・ハウス(荘園領主の邸宅)
平成29年5月15日


1 マナー・ハウスについて
ラトビア国内には大小様々なマナー・ハウスが多く残されており、歴史ある風景を今に再現しています。マナー・ハウスの正確な数は分かっていませんが、17世紀のラトビアとエストニアには、1,300軒以上存在したと考えられています。現在は、内装・外装ともに修復され、博物館やレストラン、ホテル、結婚式場、あるいは地域の公民館や学校として利用されています。
ラトビアでは、16世紀頃には荘園制度が始まっており、バルト・ドイツ人、ポーランド人、スウェーデン人またはロシア人の領主が広大な領地を所有し、マナー・ハウスで生活していました。
荘園領地には、領主の邸宅と穀物倉庫、家畜小屋、納屋及び農民の家がまとまって存在しました。多くの農民は、領主の所有する約2,000~2,500ヘクタールの土地で、農業、家畜の世話、邸宅やその庭の管理などを行っていました。19世紀の前半に農奴解放が実施されるまでは、農民には厳しい移動の制限が課されていたため、何世代も同じ土地で働き、領主に仕えました。農奴解放令後には、都市の労働者となる者や小規模な土地を所有して農業を行う者も現れました。
マナー・ハウスでは、交易を目的とした麻の生産や、家畜の繁殖、乳製品の製造、蒸留酒・ビールの製造、革製品や手工業品の製造が行われ、領主はそれらを国内外で取引しました。交易で成功した領主の中には、数万ヘクタールの土地を所有し、大規模な邸宅を建設する者もいました。マナー・ハウスは、ラトビアの農業・工業技術発展の地方拠点であったともいえるようです。
2 マナー・ハウスのご紹介
ここでは、リガから西に向かってさほど遠くないクルゼメ地方やゼムガレ地方に所在するいくつかのマナー・ハウスをご紹介します。
(1)シュロケンベカス邸宅
ラトビア国内には大小様々なマナー・ハウスが多く残されており、歴史ある風景を今に再現しています。マナー・ハウスの正確な数は分かっていませんが、17世紀のラトビアとエストニアには、1,300軒以上存在したと考えられています。現在は、内装・外装ともに修復され、博物館やレストラン、ホテル、結婚式場、あるいは地域の公民館や学校として利用されています。
ラトビアでは、16世紀頃には荘園制度が始まっており、バルト・ドイツ人、ポーランド人、スウェーデン人またはロシア人の領主が広大な領地を所有し、マナー・ハウスで生活していました。
荘園領地には、領主の邸宅と穀物倉庫、家畜小屋、納屋及び農民の家がまとまって存在しました。多くの農民は、領主の所有する約2,000~2,500ヘクタールの土地で、農業、家畜の世話、邸宅やその庭の管理などを行っていました。19世紀の前半に農奴解放が実施されるまでは、農民には厳しい移動の制限が課されていたため、何世代も同じ土地で働き、領主に仕えました。農奴解放令後には、都市の労働者となる者や小規模な土地を所有して農業を行う者も現れました。
マナー・ハウスでは、交易を目的とした麻の生産や、家畜の繁殖、乳製品の製造、蒸留酒・ビールの製造、革製品や手工業品の製造が行われ、領主はそれらを国内外で取引しました。交易で成功した領主の中には、数万ヘクタールの土地を所有し、大規模な邸宅を建設する者もいました。マナー・ハウスは、ラトビアの農業・工業技術発展の地方拠点であったともいえるようです。
2 マナー・ハウスのご紹介
ここでは、リガから西に向かってさほど遠くないクルゼメ地方やゼムガレ地方に所在するいくつかのマナー・ハウスをご紹介します。
(1)シュロケンベカス邸宅


クルゼメ地方のトゥクムス地区に所在するシュロケンベカス邸宅(Slokenbekas muiza)の存在は、すでに15世紀には知られていました。経済活動が盛んで、1788年のビールの生産量がトゥクムス地区の中で最も多かったそうです。現在、ホテル、レストランとして利用されており、道路博物館も併設されています。
(2)ヤウンピルス(※ピルスは城の意味)
(2)ヤウンピルス(※ピルスは城の意味)


ヤウンピルス(Jaunpils)は、1576年から栄えた町で、古くから家畜の繁殖を行っていました。城の近くに建設された教会には1592年の文字が刻まれています。現在は、博物館として利用されています。
マナー・ハウスには、水車小屋や風車跡も多く残されています。穀物を挽いて粉にしたり、機織り、手工業の動力源には、水車や風車が利用されていました。すでに利用されていない、基礎部分だけが残された風車跡も多く存在します(写真右下)。
(3)ドゥルベ邸宅
マナー・ハウスには、水車小屋や風車跡も多く残されています。穀物を挽いて粉にしたり、機織り、手工業の動力源には、水車や風車が利用されていました。すでに利用されていない、基礎部分だけが残された風車跡も多く存在します(写真右下)。
(3)ドゥルベ邸宅


ドゥルベ邸宅(Durbes muiza)は、1671年に最初に建設され、現在までに、何度も建て替えられています。1920年までは、邸宅と周囲の建物は個人の所有物でしたが、その後は地域の教育委員会の事務所や文化イベントの会場、子供達のサマーキャンプ会場など、地域の人々の憩いの場として利用されました。現在は、博物館として利用されています。
(4)ヤウンモク・ピルス
(4)ヤウンモク・ピルス


ヤウンモク・ピルス(Jaunmoku pils)は、1885年に当時のリガ市長が狩猟の際のロッジとして購入しました。当時は2階建ての建物でしたが、激しい嵐により損壊した後、現在のアール・ヌヴォーを基調とした、ネオ・ゴシック風の邸宅が再建されました。現在、博物館、レストラン、ホテルとして利用されています。
今回参考とさせていただいた以下の文献では、ラトビアのマナー・ハウスやラトビアの文化や歴史について詳しく記載されています。なお、写真は大使館館員が撮影しました。
●志摩園子(編)(2016)、ラトヴィアを知るための47章、株式会社明石書店
●Alberts Zarans, Latvijas pils un muizas(Csstle and manors of Latvia)
●Agrita Ozola (2009), MUIZU STASTI, Tukma muzejs
今回参考とさせていただいた以下の文献では、ラトビアのマナー・ハウスやラトビアの文化や歴史について詳しく記載されています。なお、写真は大使館館員が撮影しました。
●志摩園子(編)(2016)、ラトヴィアを知るための47章、株式会社明石書店
●Alberts Zarans, Latvijas pils un muizas(Csstle and manors of Latvia)
●Agrita Ozola (2009), MUIZU STASTI, Tukma muzejs